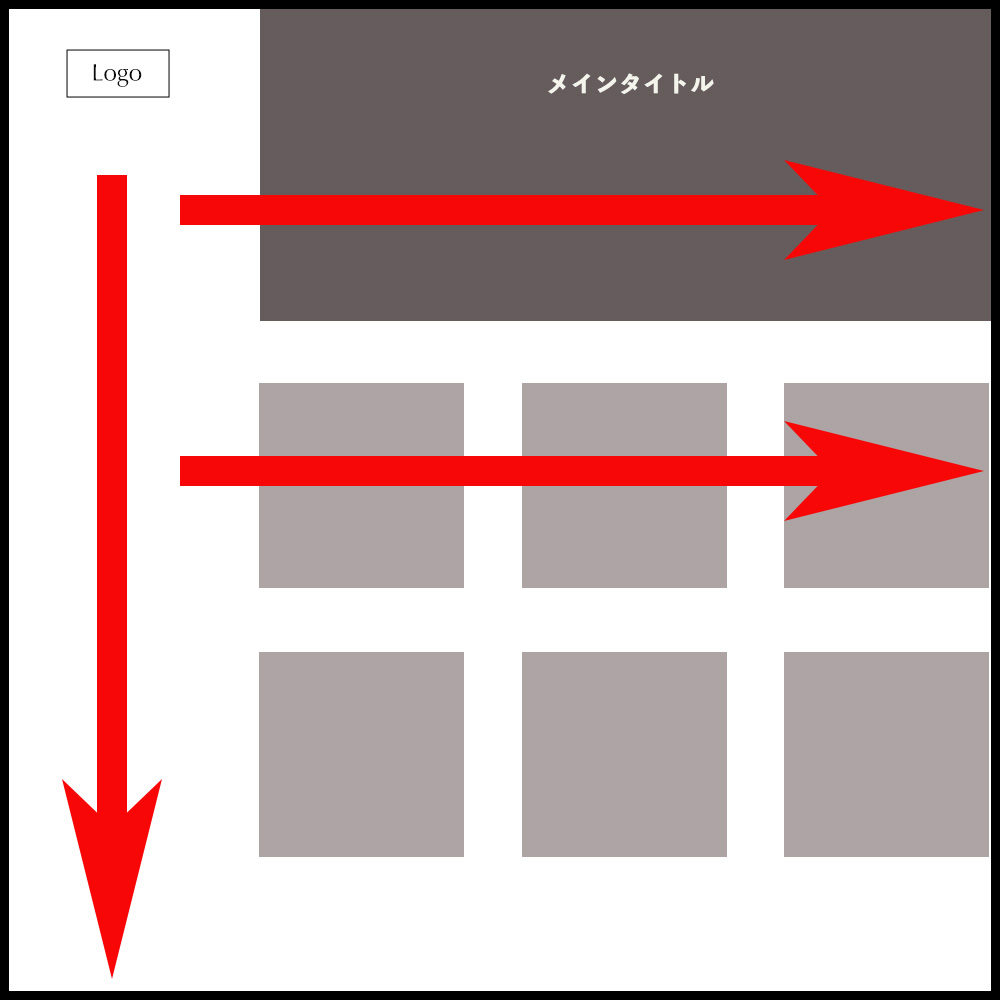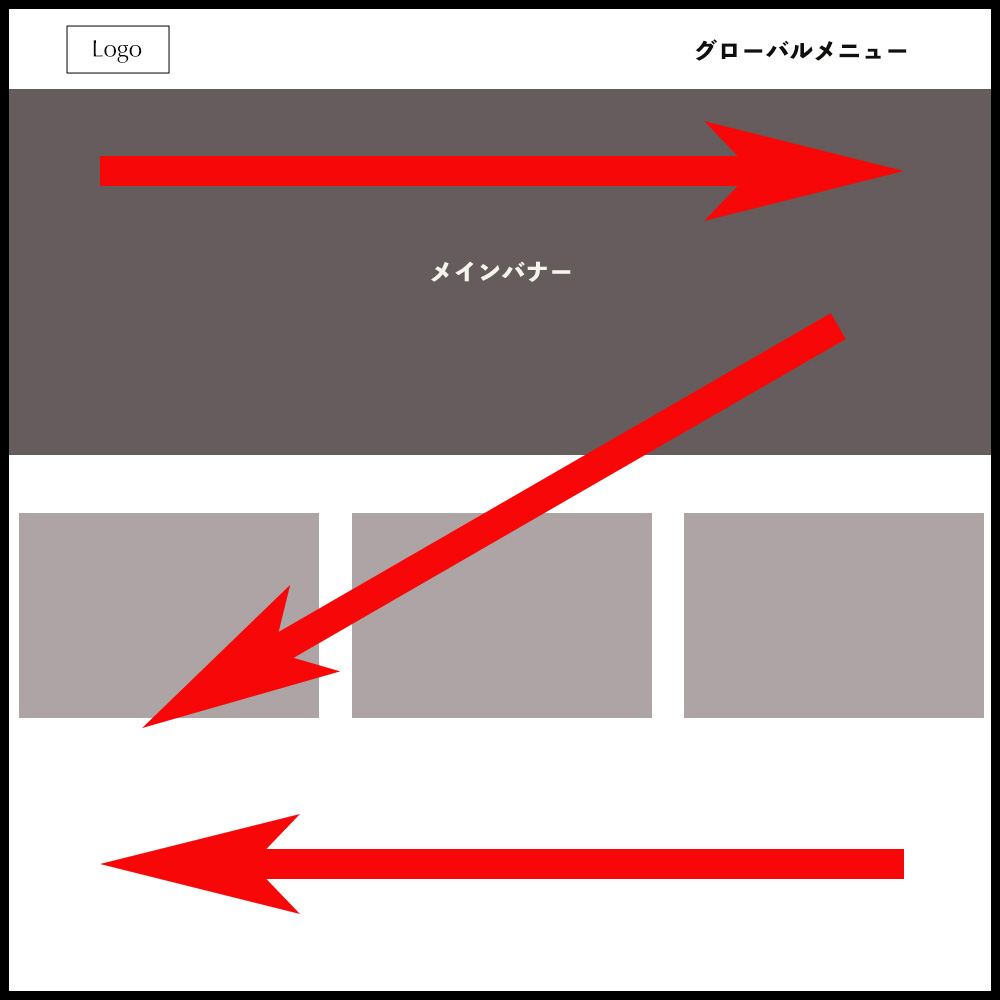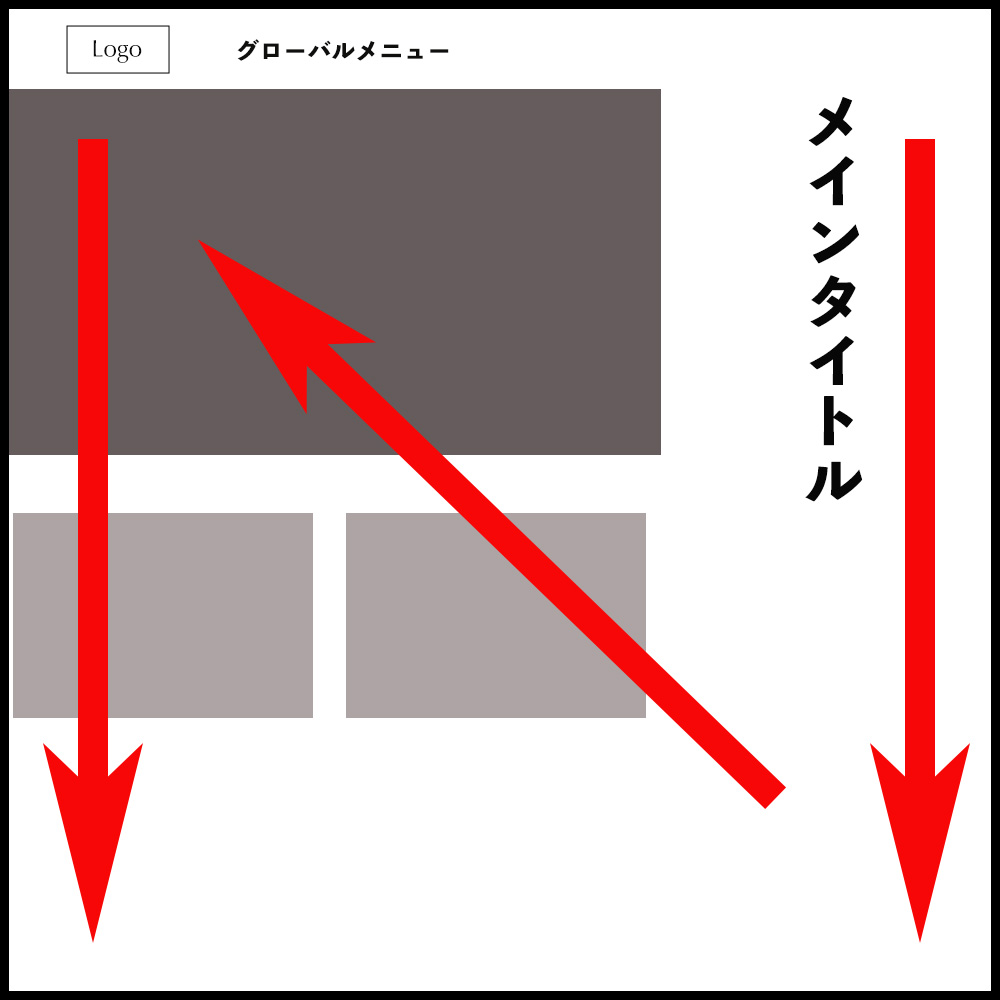Fu-KaKuオリジナルのシステム「シンクスター」を使用するとシティヘブンとFu-KaKuとの連携が可能になります。
現在β版としてご提供させていただいているサービスですが、近々正式リリース予定ですのでぜひご一読ください。
シティヘブンの店舗IDをシンクスターにコピペするだけで、Fu-KaKuで登録した
・キャストの在籍情報(プロフィール)
・キャストの並び順
・出勤情報
・即姫情報
・予約の空き状況
をシティヘブンに自動同期することができるようになりました。
個別に自動同期を有効・無効を選択することもできます。
Fu-KaKuを導入する以前から、シティヘブンで店舗を運営・キャストの在籍登録をされている場合は、
シティヘブン→Fu-KaKuへキャストの在籍を一括同期することも可能です。
(シティヘブン→Fu-KaKuの場合、キャストの並び順・出勤情報・即姫情報・予約の空き状況は同期不可。)
また、Fu-Kakuの登録源氏名がAさん、シティヘブンでの登録源氏名がBさんにしたいといった場合でも、
手動でFu-KaKuのAさんはシティヘブンのBさんと紐づけられます。
紐付け完了後、Fu-KaKuでAさんのキャスト情報を更新した際、自動でシティヘブンのBさんの情報が更新されます。
大変便利かつ効率化UPに繋がるシステムですので、ぜひ気になる方はお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから

- 2025.01.10
- by Kinta