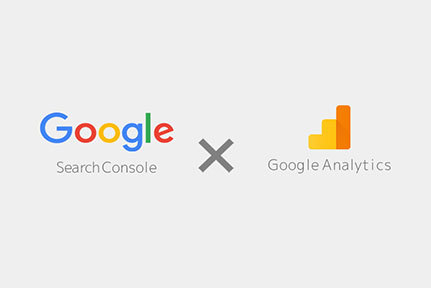今回の話題は、ネットには不可欠のブラウザについてです。
今では懐かしい、1998年にウェブブラウザー「Netscape」のソースコードがオープンソースとして公開されました。
Netscapeは、Microsoftの「Windows」と「Internet Explorer(IE)」が独占禁止法に違反していると訴えた裁判では勝利しましたが、Netscape自体は、ダウンロードしないと使用されないという、IEに比べて圧倒的不利な状況になりました。
かつては最も人気のあるブラウザーのNetscapeでしたが、オープンソースにすることでなんとか持ちこたえようとして
いるかのように見えていました。
それでもNetscapeのコードが公開されたことで、Mozilla Projectは、そのソースコードを元に、インターネットのさまざまなアプリケーションに利用できる汎用クライアントを作りました。そして2002年には、そのクライアントが純粋なウェブブラウザーである「Firefox」に生まれ変わりました。この年は、インターネットユーザーの90%以上がIEを使用していた状況でした。
しかし、Firefoxはその状況から順調にシェアを拡大していきます。まずNetscapeの愛用者や、オープンソースや「Linux」のファンがFirefoxに移行し、その後時間が経つにつれて、私も含め、多くの人に支持されるようになりました。
2010年の夏には、Firefoxのシェアが最高記録である34.1%に達しています。
ですが・・・それからは下がる一方になってしまいました。
Digital Analytics Program(DAP)が提供している過去90日間、52億7000万回分のアクセスデータによると、現在最もよく使われているブラウザーはやはり、「Google Chrome」で、シェアは47.9%でした。一方、Firefoxのシェアはわずか2.2%で、かなり少数の存在になっています。
「iPhone」人気のおかげで36.2%のシェアを持っている「Safari」や、8.3%の「Edge」はどちらもFirefoxを上回ってしまっています。一方IEは、2022年には完全にリストから外れてしまいました。
Chromeの数字は、実際には見た目以上に大きいです。それというのも、Chromeのベースになっているオープンソースの「Chromium」が、Microsoft Edgeのベースにもなっているせいもあります。またMozilla Firefoxを除けば、「Opera」「Vivaldi」「Brave」などのほかのウェブブラウザーも、すべてChromiumをベースにしています。
かつては熱烈なFirefoxファンだったユーザーの多くは、Firefoxの現状には満足していません。数々の不満の例をあげると、機能が削除され続けていることや、ひどいコーディングパラダイムや、メモリ管理の出来の悪さ、秘密裏にテレメトリー情報を収集していることなども含まれています。要するに、開発者にとっても、ブラウザーを使いたいだけの一般ユーザーにとっても、Firefoxは満足できるものではなくなっています。
また、Mozillaは、Googleと敵でもあり味方でもあるという複雑な関係にあります。Mozillaが今でも存続できているのは、GoogleがMozillaに毎年何億ドルものロイヤリティを支払っている事実があります。2022年の財務報告によれば、Mozillaの収入5億9300万ドル(約860億円)のうち、5億1000万ドル(約740億円)はロイヤリティによるものとなっています。Mozillaは今でも寄付を募っており、自らは「人々による人々のためのインターネット」であり、「既得権益を持つ大手IT企業に対抗してバランスを取る」ことを目指していると主張しています。しかし、この数字とは裏腹に、実態はそのことを不快に感じている人もいます。
例えば、MozillaのCEOであるMitchel Baker氏は、2022年に690万3089ドル(約10億円)の収入を得ていて、前年比で130万ドル増えています。また、Mozillaの年間役員報酬は平均21万3745ドル(約3100万円)だといいます。これらの数字はシリコンバレーでは決して法外なものとは言えませんが、Firefoxの市場シェアがどんどんと低くなっている現状、どう思われますでしょうか?
多くのユーザーは、その資金を役員の報酬ではなくFirefoxの改善に充ててほしいと思っているはず。あるいは、人工知能(AI)などの関連するところへの投資に使うべきと思っています。
私はFirefoxが、その最初の名前である「Phoenix」(不死鳥)のごとく蘇るのを期待したいところですが、いよいよ今度こそFirefoxは消えてしまう運命なのかもしれませんね・・・。

- 2024.01.19
- by Hiro